2025年5月13日火曜日
2025年5月12日月曜日
出張講義 近見小学校6年生の遠足ガイド(5月2日)
5月2日(金)の今治市立近見小学校6年生(47名)の遠足は、今年も近見地区のまちおこしグループ「しまなみ海道周辺を守り育てる会」(村越定信会長/以下、守る会)がサポートする形で、校区内の史跡めぐりを行いました。コースは、9時過ぎに来島海峡海上交通センター(以下、来島マーチス)の視察に始まり、相の谷1号墳、大浜灯台跡地、小湊城跡・城慶寺、湊石風呂とつづいて、最後の大浜八幡神社が13時半に終了となりました。一般に遠足といえば、遠い目的地まで歩き、お弁当・お菓子を食べて遊んでから折り返すという形態をとりますが、ここ7〜8年ほど、近見小学校では上記のコースを歩きながら、ふるさとの魅力を再発見する取り組みを地域と連携しながら行っています。守る会と小学校からの依頼で、本学からは地域連携センター長の大成経凡先生がこの遠足に参加しています。
来島マーチスと大浜灯台跡地は、それぞれ海上保安庁の職員が来島海峡の安全や灯台の歴史・役割など、海事思想の普及に関する説明を行いました。マーチス展望デッキからの眺めに、児童は喜びをかくせない様子で、校区が自然環境にめぐまれた場所にあることを再認識できたようです。相の谷1号墳では、今治市教育委員会文化振興課の職員が、同古墳の歴史的価値の説明を行いました。愛媛県最大の前方後円墳(全長約82m)が、まさか自分たちの学校のすぐそばにあるとは思わなかったようです。同古墳を見学できるようになったのも、育てる会の会員がコツコツと草刈りや雑木刈りをつづけてきたからで、今回も遠足に合わせて前日に草刈りを行ってくれました。会では、将来的にこの古墳を国指定史跡にしたいようで、そのためには未来への種まきで、地元の子供たちに価値を知っておいて欲しいという思いがあるのです。大浜灯台跡地についても、現在は不用の施設となっていて、将来的に国から用地の払い下げを受けて地域活性化の拠点にしたいと考えています。灯台はすでに撤去されてありませんが、大浜灯台が明治35(1902)年に初点灯した当時の煉瓦塀と石垣は残っています。これを残したままでの払い下げを求めているところです。
 |
| 相の谷1号墳 |
 |
| 来島マーチスの展望デッキと潮流信号 |
大成先生は、小湊城跡以降のガイドを担当しました。小湊城跡は、村上海賊ゆかりの海城であることから、日本遺産にもなっています(城慶寺も来島村上氏ゆかりの寺院であることで日本遺産に認定)。小高い丘陵に登ると、とても見晴らしがよく、航路をにらむ場所に海賊たちが拠点を設けたことを児童に理解させました。この点は、同じ伊賀山丘陵にある来島マーチス・相の谷1号墳・大浜灯台跡地も同様で、来島海峡航路の重要性を考えた場合、その一帯は海上交通管制でとても大切な場所といえます。守る会と大成先生は、その一帯を将来的に今治市海事公園第1号にしたいという夢を持っているのです。
 |
| 大浜灯台跡地 |
.jpg) |
| 大浜灯台(絵葉書より) |
城慶寺でお弁当を食べた後は、海岸線の一般道を通って大浜八幡神社へしばらく歩きました。その途中に湊石風呂跡があり、場所の確認と簡単な説明を行いました。大浜八幡神社では、神社の参拝方法や拝殿に飾られた絵馬の価値などについて説明しました。何気なく見るのと、価値を知ってから見るのとでは、児童たちも得られる感動が違った様子でした。そして最後に、この日の遠足のために、調整役として動いてくれた守る会の皆様にお礼の挨拶をして終了となりました。この年齢の子供たちに、郷土の歴史を教えることは簡単ですが、興味のもたせ方がとても大事になってきます。大成先生は小学6年生の時、担任の先生が教えてくれた「近見小学校の裏山に愛媛県最大の前方後円墳がある」「今治市役所の市庁舎は、世界的な建築家・丹下健三が設計した」という言葉に心をときめかせたようです。まさか将来、相の谷1号墳の保存整備や丹下健三マンガの制作に自身が関わろうとは夢にも思わなかったとか。来年度新設の地域未来創生コースでは、近見地区のまちづくりにも関わりたいと考えております。
 |
| 来島海峡を眺めながら移動 |
 |
| 大浜八幡神社 |
2025年5月9日金曜日
授業紹介 「地域活性化論」 小島の芸予要塞跡を散策(5月1日)
5月1日の「地域活性化論」(大成経凡)は、39名の学生(うち1名聴講)が来島海峡に浮かぶ周囲3㎞の小さな島〝小島〟(おしま)を散策しました。ここ3年間は、後期の「地域交流演習」で小島散策を実施していましたが、新緑の時季に前倒しして、入国して間もない留学生に旅行気分を味わってもらうことにしました。参加者の国別内訳は、ミャンマー26・日本9・中国4で、このうちミャンマー人5名ほどは、昨年秋に聴講で参加しています。行く度に新たな発見や美しい景観に癒される小島は、今治市民にとっても小旅行の気分にひたれる癒しの観光スポットなのです。
アクセスについては、波止浜港から来島・小島・馬島行きの定期航路の渡船を使用しますが、大勢の人数や授業時間内での実施を考えた場合、その船をチャーターした方がプレミアム感を味わうことができます(波止浜〜小島は片道10分)。大成先生は4月29日にも「アシさとクラブ」のウォーキングイベント〝みちくさんぽ〟で40名余りの老若男女に小島ガイドをしていて、この時は3時間ほど島に滞在したようです。今回は、その時のような詳しいガイドは控え、簡単な歴史解説を交えながら、どれだけ満喫できるかに注力しました。
 |
| 頂上の観測所跡 |
小島には、陸軍が日露戦争に備えて明治30年代に築いた要塞の遺跡が、良好な状態で残されています。当時の要塞の構造(建築技術)や時代背景(近代史)を知る貴重な歴史遺産であることは言うまでもありません。また、トトロ(椿のトンネルの遊歩道)やラピュタ(中部砲台)といったジブリ映画に出てきそうな場所があって、どこか違う時空に迷い込んだ錯覚を感じることができます。インスタ映えスポット満載なのです。このため、最近は若い二人組の女性観光客をよく見かけるようになりました。一方で、島民が現在4名となって耕作放棄地が増えたことで、イノシシの被害が深刻化しています。
 |
| トトロの森のような光景(ツバキのトンネル) |
 |
| 28㎝榴弾砲レプリカ前で |
遺跡が保存状態良好であるのは、大正時代に兵器の進歩等で要塞の廃止が決まり、昭和2(1927)年に波止浜町が国から払い下げを受けて公園整備したためです。この背景には、大正13(1924)年に国鉄波止浜駅が開業し、観光振興を図ろうとした当時の町長・原眞十郎翁(ハラプレックス創業者)の先見性がありました。まさに〝百年の大計〟で、昭和30(1955)年に波止浜町が今治市に編入合併された後も、今治市はここを観光名所として大切にしました。昭和52〜53(1977〜78)年にツバキの遊歩道を整備したのもその一つ。しまなみ海道開通後(1999年〜)も、南部発電所の屋根修理や港待合所の新設、28㎝榴弾砲レプリカの設置(松山市より譲渡)など、漸次テコ入れを図りました。想定外だったのは、島外から泳いで渡ってきたイノシシが繁殖し、遊歩道沿いの景観が荒廃したことです。これは、来春新設される地域未来創生コースで解決策を模索したいと思います。
小島の頂上は標高100mで、要塞当時は観測所がありました。それだけに、360度パノラマの絶景を楽しむことができます。頂上滞在は10分余りでしたが、その眺めが〝今治の魅力〟として認識できたなら幸いです。
 |
| 頂上で見つけたハートマーク💓 |
 |
| 復路の波止浜湾 |
2025年5月8日木曜日
国際観光ビジネスコース 半島四国八十八か所ウォーキングに参加しました
2025年4月26日
今治東ライオンズクラブ主催の「半島四国八十八か所ウォーキング」に今年は留学生44名が参加しました。
国際観光ビジネスコースは、科目「日本語学入門」の授業の一環として毎年このイベントに参加しています。今年は晴天に恵まれ、体調不良の学生もなく、元気に出発することができました。
2025年5月7日水曜日
授業紹介 「日本を学ぶ」朝倉古墳めぐりと市民の森・フラワーパーク(4月28日)
4月28日(月曜)の「日本を学ぶⅠ」(大成経凡)は、座学で前回授業の振り返りと今回授業の予習を行ってから、学園バスに乗って朝倉地域の古墳めぐりに出かけました。学外授業に参加した学生は40名で、国別内訳はミャンマー19・中国12・日本4・インドネシア3・スリランカ2となります。
前回は前方後円墳の妙見山古墳を見学しました。日本独自の形態の古墳ですから、留学生の目には不思議な光景として映ったことでしょう。日本人の目にも、公園の展望所が国指定史跡の遺跡というのは、不思議な感覚を抱いたのかも知れません。ちなみに、愛媛県下最大の前方後円墳「相の谷1号墳」(全長約82m)については、来島海峡にのぞむ伊賀山丘陵、つまりは今治市近見地区にあります。妙見山古墳同様に丘陵上にあって、海を意識して造られた点に注目してもらいました。
そして今回は、海岸から少し離れた山間部をイメージする朝倉地域へ向かいました。先般、山林火災にあった笠松山の麓に野々瀬古墳群は所在しています。保存状態の良い円墳20基ほどが現存し、そのうちの一つ「五間塚古墳」は直径15~16mあって、横穴式石室は大人が立ったままの状態で入ることができる大きさです。興味のある学生に入室を勧めたところ、半数以上が実際に中に入って、石組みの状態など、当時の土木造成技術を学ぶことができました。おそらくこの古墳については、飛鳥時代に土地の有力者の墓として造立されたもので、地元では〝王塚〟とも称されています。幕末期にここを訪ねた国学者の半井梧菴(なからいごあん)は、これらの円墳を古代人の住居と勘違いしたようで、そのくらい状態の良さは訪問者に大きな驚きを与えます。今治市民でさえもが、ここを訪ねたことのある人は少なく、もっと知って欲しい歴史遺産といえます。
 |
| 五間塚古墳の外観 |
 |
| 五間塚古墳の石室入口 |
 |
| 五間塚古墳の内観 |
同所で最大の円墳「七間塚古墳」を見学した後は、学園バスを市街の方向へ少し戻し、周越道路沿いにある円墳「樹之本古墳」の前で記念撮影を行いました。この古墳からは、明治末期に青銅鏡などが発見され、貴重な出土遺物は東京国立博物館で収蔵しています。その青銅鏡は、わが国最大の前方後円墳である「大仙古墳」(仁徳天皇陵)出土の青銅鏡に酷似するとかで、大和朝廷との結びつきを想定させます。相の谷1号墳についても、奈良市にある大王クラスの宝来山古墳の3分の1サイズで築造されていることが近年指摘され、大和朝廷と古墳時代における今治地方の結びつきを想定することができます。樹之本古墳の場所からは来島海峡大橋が遠望でき、これも海を意識した古墳なのかも知れません。
2025年5月2日金曜日
2025年5月1日木曜日
今治西高校で出張講義(4月23日)
昨年度につづき、今治西高校2年生の「総合的な探究の時間ZEST」において、本学地域連携センター長の大成経凡先生が出張講義を行いました。同校では令和8年度から国際科コースを新設予定で、その準備段階としてZESTの中に国際的視野を醸成するための探究授業を設けております。その一つが、大成先生の〝今治の地域課題と向き合い、その解決方法を模索する授業〟であります。昨年度は「外国人にやさしいまち」「方言の価値を見直そう」「特産物を広くPRしよう」などのテーマがありました。グループごとに分かれて探究を進めた結果、最終的にプレゼンの大会に出場する班もありました。
今年度は各グループ4人ずつ20人の生徒が受講しますが、昨年一人だった男子生徒が数人増えていました。この日は、各班の代表が研究テーマや課題の現状把握について発表し、研究の進め方などを大成先生に質問しました。各班のテーマは、1班「今治サイクリングの新たな未来~世界に魅力を伝えるには~」・2班「多文化共生でよりよい今治にしよう」・3班「今治の特産品を海外へ」・4班「今治と姉妹都市の名物でコラボしてお互いにアピールしよう!」・5班「外国人サイクリストに今治の食について知ってもらおう」というものでした。
 |
| 講義の様子 |
1班と5班については、実際に海外のサイクリスト(インバウンド)から、どこで、どのような内容のヒアリングをすればいいのか質問がありました。これに対し、大成先生自身も、道の駅や橋の出入口などで待ち構えて、ヒアリングを行ってみたいという希望を持っているようで、一緒にチャレンジしてみようかという提案がありました。まさに「YOUは何しにSHIMANAMIへ?」であります(笑)。YOUの出身国は? 来日の目的は? どのくらい滞在予定か? 他の観光地はどこを訪ねたか、これから訪ねるのか? 日本で楽しみにしている食べ物は? 今治の印象は? 今治での宿泊を予定しているのか? まずは、彼らのニーズを知らないと、課題解決に向けた方策も描けません。
2班については、今年度から今治市役所市民参画課内に多文化・共生社会推進室が新たに設けられた情報を伝えました。減りゆく市の人口に対して、産業界から人材不足を嘆く声があがっています。これを技能実習生だけでカバーするというのでは、根本的解決にはいたりません。外国人労働者が家族と一緒に住みたいと思えるまちに変えていくとすれば、それには一体何が必要か。本学の卒業生の中には、N2(日本語能力検定2級)を取得して、通訳の就労ビザで今治市内の企業に就職している中国人らがいます。彼らの中には、将来的に日本へ家族を呼び寄せたいという希望を持つものもいます。卒業生どうしが結婚して、今治市内の同じ職場で働いている中国人もいます。その卒業生たちに共通するのは、今治市が好きだということです。好きになるためには、そうした機会を在学中につくる必要があり、大成先生の学外授業にはそのねらいもあるようです。
 |
| 各班の探究テーマ |
以上のように、各班にアドバイスをすることで、大成先生は自己紹介に替えさせていただいたようです。50分授業はあっという間です。今後は50分授業を1回、50分2回連続授業を2回予定しており、プレゼンテーション能力の向上も図っていけたらと思います。本学では、来年度から地域未来創生コースを新設予定ですが、ZESTがそれに向けた試金石となれば幸いです。
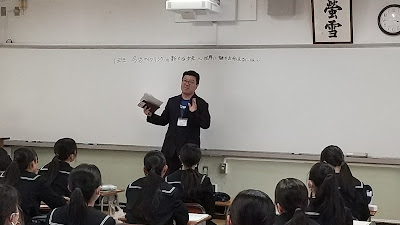 |
| 大成先生 |













