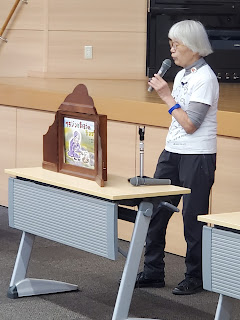10月24日(木)と10月31日(木)の「地域交流演習」(大成経凡先生)は、履修生を2つのグループ(A・B)に分けて、来島海峡に浮かぶ小さな島「小島」(おしま)へ学外授業に参りました。24日のB班は今年秋入学のネパール人31名(ほか2名の教員・通訳)、31日のA班は今年春入学のネパール人18名とミャンマー・中国・日本・ベトナムの混成からなる45名(ほか2名の教員・通訳)の編成となりました。B班については、履修生以外の秋入学のミャンマー人も加わり、大所帯となりました。
 |
| チャーター船の船内(A班) |
〝海を見たい、船に乗りたい〟という秋入学の留学生の希望を叶えるため、少し無理をした感があります。幸いにも、波止浜港からの渡船は貸切りとし、他の客に気兼ねすることなく片道10分の船旅を学生たちは満喫している様子でした。渡船からは波止浜湾の造船所群を沖から観察することができ、本航路は産業観光の要素も備えています。すでに㈱しまなみの遊覧船が、来島海峡の急流や橋の景観と併せ、この産業観光を推しのスポットに挙げているところです。
 |
| 小島へ向かうB班のチャーター船(奥が小島) |
本授業では、すっかり秋の鉄板コースになりつつある小島のフィールドワーク。周囲約3㎞、頂上の標高100mの島内には、明治30年代に対日露戦争に備えて陸軍が築いた要塞(ようさい)の遺跡が残されています(砲台跡・発電所跡・弾薬庫跡・観測所跡・探照灯台跡・雁木など)。これを、戦争遺跡という負の歴史でとらえるのではなく、明治期の建築技術の学習や要塞廃止後に公園として整備した地域活性化(観光)の観点からとらえる必要があります。留学生が多いことで、時代背景や軍事思想の詳細をガイドできない大成先生はもどかしかったようですが、小島が今治市にとって貴重な観光資源であることを認識できたなら、渡船をチャーターした甲斐もあったことでしょう。
 |
| 波止浜湾(A班) |
現在の島民は10名ほどのようで、島内の耕作地は放棄されて〝荒れ放題〟となっています。そこへ島外から渡来したイノシシが繁殖し、遊歩道は歩行しづらいほどに土砂が散乱・堆積する有様です。遊歩道沿いに植えられたツバキの根がむき出しになるほど、環境の悪化はここ数年深刻です。しまなみ海道開通後に脚光を浴び、〝海上の城・ラピュタ〟と称されるなど、保存整備も行き届いて海道有数の推しのスポットと自負していたのですが…。一方、ほぼ同時期に芸予要塞として築造された大久野島(広島県竹原市)は、SNSが普及する中で〝毒ガスの島〟から〝ウサギの島〟へ変貌を遂げ、すっかりインバウンドで賑わう観光の島となりました。
 |
| 中部堡塁(A班) |
参加した学生全員が小島は初上陸とあって、〝イノシシの島〟への変貌に驚くことはありませんでした。不思議な場所を訪ね、頂上からの眺めが抜群に良かったと感じたはずです。頂上の観測所跡は敵艦の位置を捕捉するだけあって、360度パノラマの眺望が来頂者を喜ばせます。下草が刈られていれば、寝そべるなどして、さらにリラックスできたことでしょう。島滞在時間は1時間半しかなく、頂上で10分楽しんだ後は、来た道を急いで下りました。渡船が到着するまでの間、学生たちは桟橋から来島海峡第3大橋を眺め、撮影に興じていました。大成先生曰く、令和8年度入試から採用される新コース「地域未来創生コース」(準備中)では、小島の魅力と課題を徹底的に検証するとのことです。
 |
| 頂上でくつろぐ留学生(A班) |
 |
| 頂上の観測所跡(A班) |
 |
| 発電所跡(B班のネパール人留学生) |