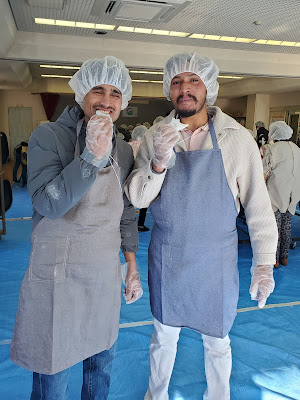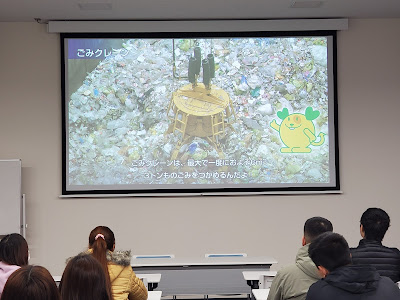12月11日(水曜)午後、今治西高校の総合的な探究の時間「ZEST」は最終回を迎えました。2年生を対象とし、文系・理系それぞれで様々な講座がある中で、本学の大成経凡先生は、グローカル講座(グローバル&ローカル)に4月以降7コマ参加させていただきました。大成先生の役割は、テーマ別にグループ分けした5つの班に対して、探究の進め方やプレゼンの仕方をアドバイスするというもので、生徒個々の成長につながったなら幸いです。
改めて各班のテーマを確認しておくと、「外国人が住みやすい今治にするために」(1班/4名)・「大島石で地域おこし~今治から世界へ~」(2班/2名)・「今治を盛り上げよう!~おにぎりを通して~」(3班/4名)・「やさしい日本語を通した外国人との交流」(4班/3名)・「方言から見えるその地の魅力」(5班/4名)というものでした。
前回のプレゼン発表(10月16日)の審査をへて、5班が12月15日に東京で開催される2024年度全国高校生フォーラムに出場することが決まりました。そのプレゼンは、ポスターセッションで4分間の英語スピーチを行うというもので、この日はその予行演習も兼ねていました。また、2班は12月21日に愛媛大学附属高校で開催される国際会議「ESD Youth Summit 2024」に出場することが決まり(自ら参加表明)、こちらは他の班同様に7分間のプレゼンを行いました。
前回のプレゼンから3コマの授業をへて、内容を精選したり、新たな項目を加えたりと、各班それぞれで成長が見られたように思います。また、7分間の時間制約を受けて、前回よりもいいパフォーマンスを発揮できなかった班もありました。成績を評価されると判断してか、高校生らしいハツラツさに欠け、無難にまとめようとする点が少し気になりました。地域活性化に関係する取り組みは、聴いている側をワクワクさせるような話術があってもいいと思います。
この日は、大成先生から手厳しい改善点や疑問点が多く示されました。前回よりも進化してチームワークを発揮した1班は、大いに褒めたたえました。本学留学生に聞き取り調査をした4班は、この講座を代表して校内発表してもらうことを終了後に担当教諭と決めました。フィールドワークをした成果は、分析することで自分のものとなり、自分の言葉で自信を持って相手に伝えることができます。3班のご当地おにぎりは、ぜひとも本学の学生祭で模擬店を出して販売して欲しいと思いました。
今治西高校は大成先生の母校でもありますが、県内有数の進学校ゆえに、探究の時間にさく時間を多く割くことはできません。部活動のしばりもあって、東京や松山で開催される大会に最初から出場をあきらめている班もありました。モチベーションを高く保つのが難しい点もよく理解できましたが、グローカルな視点を培う機会を持てたことは財産になったことと思います。研究の手法を学ぶことよりも、身近な地域に関心を持つことがまずは大切で、積み重ねた努力は無駄にならないと思います。お疲れ様でした。
 |
| 講評を述べる大成先生 |
本学でも令和8年度から探究学習をふんだんに取り入れた新コース「地域未来創生コース」を開講予定ですが、今治を学びのフィールドとし、個々の目標とする将来像へのサポートを行いたいと考えております。3月23日(日)のオープンキャンパスで新コースの概要説明と模擬授業を実施したいと思います。乞うご期待!